先週末よりハワイ大学はクリスマス休暇に入り、オフィスの床をワックスがけするため、仕事もアパート。しかし、これまでは毎日往復1時間の徒歩通勤をしていたのを急に止めて、外出も食材などの買い出しのみとなってしまったこともあり、なんとなく体調も気分も停滞ぎみ。
そんなこともあり、そろそろ「歩きたい!」って足が叫んでいるようにも思えた。
クリスマス休暇といえども雨期。天気がいまいちだったWeekdayに比べて、昨日金曜からなんとか午前は晴れていた事と、土曜の今朝はなんとか青空も雲間に見えていたので、意を決してハイキングに出かける事にした。
今日は、いつもとは違いバスを使ってのアプローチ。でも、バスを使うのは行きだけ。帰りはそのままアパートに歩いて帰って来れるというルート。
朝8時45分、いつも利用するTheBusのNo.6に乗る。University Ave/Beretaniaで下車。そこからS.King Stを東に20分ほど歩き、Kapiolani Blvd/Kaimuki Aveのバス停からTheBusのNo.14(St.Louis Heghts行き)に乗る。もちろん、トランスファーチケットを貰っているので、料金は$2だけ。しかし、No.14というのは1時間に1本しか走っていないため、30分程度バス停でボケ〜と待つことになるが。。。
待望のNo.14のバスに乗り、つづら折れの急坂をバスはどんどんと登って行く。ワイキキが見え、ダイヤモンドヘッドが見え、さらにダイヤモンドヘッドよりも高いところになると、住宅の状況も一変。超高級住宅地である。オシャレなクリスマスの飾り付けをしたり、芝が綺麗に刈られていたり、大きな邸宅ばかりである。
終点(というか、バスはそのままUターンして戻って行くのだが)で下車。ほぼ10時。
ただの住宅地!なので、どこから登るのかしらと一緒に下りたおじさまに聞いたら、そこを下れと。バスの運転手も指差してくれた。

バス停から1ブロック先の公園入口に到着。10:05通過。

導入路は舗装され、周囲にはハワイには珍しい?針葉樹が!
針葉樹特有の香りを楽しみながら雨上がりの道を進む。この香りから、カリフォルニアのヨセミテバレーを思い出した。ハーフドームなどを見渡せるグレッシャーポイントという有名なViewPointまでバスで行き、そこから長男とバレーまで下った。途中、子どもの顔ほどもある大きな松ぼっくりを拾ったりした。とても、懐かしい思い出。

公園の終点(駐車場の奥)には、野生の鶏が!

ここから本日のWaahila Ridge Trailが始まる!10:15通過!

すでにマノアバレーは眼下に見下ろせる高さ!

あいかわらず赤土の道。

尾根の道は周囲が見渡せると気分も爽快。アップダウンを繰り返しながら進む。

マノアバレーとは反対側(東側)のパロロ(Palolo)バレー。

尾根道特有のアップダウンを繰り返すが、細かいため、それほどキツい高低差はない。マノアバレーからも見えるゆったりとした尾根そのもの。

陽のあたる道は御覧のように乾いているが、このところの雨で日陰はぬかるみ、かなり気をつけないと滑りそう。

来し方を振り返ると。。。結構登っているんだ。

登っては下り、下っては登る。今回のトレールでは、途中3名の男性グループと、1組のカップルを追い抜き、4名の韓国系(韓国語を大声で話しながら下ってきたから)のおじさま/おばさまとすれ違う。さらに、帰路では1組のカップルを追い越した。休暇だからなのか、人気があるトレールなのか。。。

こんな木を見ると熱帯雨林のハワイなんだと感じる。でも、この根の道はとても滑るんだ!

こんな明るい道ばかりだと良いんだけどなぁ。。。

途中、こんなキノコを見つける。

ワイキキが見えた!

さらに来し方を振り返ると恐竜の背中のような尾根の先にはダイヤモンドヘッドが!

相変わらずこんな木のトンネルをくぐる。

本日のトレールのView Point(と勝手に決めた)にて小休止。11:00到着!
背景(足元)はワイキキ!(超小型三脚を使用)

パノラマ写真を撮ってみた!(いつものようにクリックで拡大)

ViewPointからさらに進むと、見覚えのある周囲の景色と看板を発見!
Kolowalu Trailとの合流地点に11:10到着。
尾根の道はここまで。コレより先は未整備のため、入るべからずと記載してある。さて、天候もいまいち。雨が降ってきそうな気配。ぬかるむ道がさらにスリップするため、早々に見覚えのある帰路へと進む。

見覚えのある大きな木。でも、周囲にはこんなに雑草は生えていなかったけど。。。

倒木もそのままだなぁ...管理はどこだぁ。。。

3回目の分岐地点に11:45到着。ここまで来るとすぐにトレールは終了だぁ。

あいかわらず、シェルターの脇には赤い花。。。

トレールの入口は11:50通過。下ると晴れる、相変わらずの天気男?。
アパートまでの道中、シャワーのような細かい雨が降ったり止んだりしたけど、汗をかいた身には心地良い感覚。しかし、赤土だらけの靴はどうしたものか。。。帰宅したら洗わないといけないなぁ。。。
そして、アパートには12:15帰着。
日頃、アパートから見てる尾根を巡るハイキングも良いもんだと思った。






































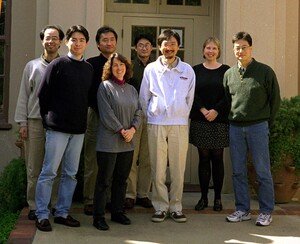
最近のコメント